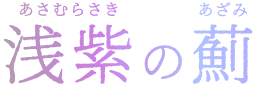浅紫の薊 第1章 第1話『桜』
1
春の魔力は恐ろしい。
さながら、何か新しい挑戦を試みろと言わんばかりに急かしてくる。太古の人々が、春は始まりの季節であると定義付けてしまったが故に、こうしてその風習が現代にまで根付いてしまっているのだろう。まったく、別に他の季節でもよかったではないかと、わけのわからない悪態の一つでも吐きたくなる。
はて、春の陽気言い換え妖気に当てられたか。
ブレザーに袖を通しながら、そんなことを考える。
部屋を出て階下に降りると、姉さんは既に仕事に出掛けたらしく、リビングの座卓の上には「行ってきます」と書かれ、なおかつキスマークが滲んでいる置き手紙が鎮座していた。
トーストで簡単な朝食を済ませ、遅刻にならないようガラケーで時間を確認しつつ通学靴を履く。扉の装飾の隙間からは暖かな陽気が射しており、足元を淡く照らしていた。
「行ってきます」
誰にともなく小さく呟くと、扉の取っ手を押し、いざ春一色の世界へ。
四月、春、新学期。だからと言って、世界が大きく変わったわけではない。それでも心がすっと軽くなり、少しばかり踊るのはなぜだろう。普段と変わりない住宅街が、ほんの少しだけ違った雰囲気に包まれているような気がする。
「これじゃあ本当に春の妖気みたいだ」
部屋で寝ぼけ交じりにほざいた冗談が、なんだか本当のことのように思えて苦笑が洩れる。
さて、そろそろ学校に向かおう、と足を前に動かそうとしたまさにその時、見知らぬ幼子が僕の横を走り抜けた気がした。
思わず振り返る。が、そこには誰もいない。
気のせいだったか。そう結論付け再び足を動かそうとしたが、視界にお向かいさんの家が入り、再び足は止まる。そうだ、流石に今日からは先月までのように素通りするわけにはいかない。
本来ならばそのまま右折して通学路へ向かうのだが、今日は向かいの家に視線を向けたまま立ち尽くし、数秒の間を要してから意を決してそちらに歩を進める。
彼女は取り合ってくれるだろうか。
インターホンを鳴らし、出てきた彼女の母親に事情を話してからお邪魔させてもらう。向かう先は二階の一室。何となく、その向こう側の景色が目に浮かんだ。
夜の延長戦と言わんばかりに真っ暗な部屋の中。そこからカタカタとパソコンのキーを叩く音だけが虚しく響く。カーテンは全て閉めきられており、パソコンの画面が放つ青白い光だけが、虚ろな瞳を持つ少女の顔を照らし続けていた。きっと彼女の脇には何本ものゲームソフトが積み重なり、ある種の山と化しているのだろう。そう考えると少し笑えてきた。
僕は想像を続ける。
コンコン。
そんなキーを叩く音しか響いていなかった部屋に、不意に扉をノックする音が響いた。自分が発する音以外の不協和音に少女が驚いたように、だがそれでもマイペースにのろのろと顔を上げる。
彼女が見詰めるのは扉を隔てて向こう側にいる人物。つまり、ノックした人物に他ならない。この僕だ。
「咲、いるんだろ。開けてよ」
ノックした後に彼女の名を呼ぶ。しかし一向に返事はなく、そればかりか暫くするとこれが返事と言わんばかりに、再びキーボードを叩く小気味よい音が扉を隔てて響いてくるではないか。
毎度お馴染みの展開。相変わらずの事に思わず溜め息を一つ。このような生活がかれこれ一年も続いているのだから、強情・頑固と言う他ないだろう。
こうなったら背に腹は代えられぬ。
「いつまで引き込もってんだよ。いい加減出てこい」
最後の警告のつもりで声を掛けるが、やはり何の返事もない。それどころかキーを叩く音が大きくなるばかりである。こうもコミュニケーションが取れなくては話が一歩も前に進まない。仕方なく咲の母親から預かった合鍵を使い、部屋に入ることにした。年頃の女子の部屋に勝手に侵入する不届きを許せ。
がちゃり。
固い感触と同時に扉が開く。
流石にこの異変にはすぐに気付いたらしい咲は、刹那、扉を開けた僕の方に振り返った。
「え、嘘、なんで」と咲は当然ながら狼狽を顕にする。「どうして鍵を」
「忍さんのご厚意だよ。さあ、学校に行くぞ」
ひらひらと鍵をかざしながら簡単に説明すると、咲の腕を掴み立たせようとする。が、彼女はそれを拒むように手を払い除けた。
「行かないから。学校なんて行かない」
「お前なあ」
この期に及んで、まだそんなことを言うか。しかし彼女の境遇を思うと、その台詞も喉を出ない。
何とかして機嫌を取るべきかと思索するものの妙案が咄嗟に浮かぶはずもなく、嫌だ嫌だ、と駄々をこねる彼女を見ているしかない。だが、ここまで来たのだから引き返すという選択肢は無いに等しい。
結論、あまりにも頑固なので、僕は最後の手段を決行することにする。できればこの手だけは使いたくなかった。
「兎に角、始業式くらい来なよ」
「え、あ、わっ」
荒療治だが、僕はノートパソコンを奪うと同時に、彼女襟首を掴み、やや強引ながらも外に引きずり出す。慌てて咲は襟首を掴んでいた僕の手を払い除けるが、生憎ノートパソコンは未だこちらの手の中だ。
「ちょっと。パソコン返してよ」
「うん、返すよ。長時間これ持ってたら重いし。まあ、今日学校に行くんだったらの話だけど」
「うっ」
パソコンを人質に取られたからには咲が僕に逆らえるはずもない。何せネットは彼女の生活スタイルの一環なのだ。こうでもしなければ梃子でも動かないことを僕は熟知している。
葛藤で数秒を費やし、その末ようやく「わかった」と渋々呟くと、一旦部屋に戻り、五分もしない内に制服に着替えて戻ってきた。身嗜みなど毛頭気にしていないのか、髪は所々はねているままである。
女の子なんだから、と注意を促そうかとも思ったが、時間も差し迫っているため、結局何も言わずに彼女を連れて階下へ降りる。一階には満足そうな笑みを浮かべた咲の母親の忍さんが佇んでおり、奪ったパソコンと預かった鍵を彼女に手渡すと、同じように僕も笑みを浮かべた。
「じゃあ、忍さん。咲を連れて行きますね」
「はい。いってらっしゃい、咲、悟くん」
その言葉に見送られて僕らは揃って石沢邸を後にした。
2
互いに無言のまま住宅街を抜け、ようやく通学路に出た時のことだ。
「ひどい」と開口一番に咲は皮肉を口にした。「私からパソコンを奪うなんて」
何故に皆勤生徒の僕が不登校生徒に責められなくてはならないのだ。
「仕方ないでしょ。こうでもしなきゃ、咲、学校に来ないじゃん」
「……」
元より非は咲にあるため、彼女は何も言い返せず俯きがちに僕の隣を歩く。
石沢咲は書いて字の如く、由来は花が開花するように成長してほしいという願い。家が向かい同士の幼馴染みであり、幼い頃からの顔見知りであるため、付き合いは誰よりも長いと自負している。そのため、石沢婦人の願いが一切叶っていないことも周知の通り。
ある一件から重度のパソコン依存性で引き込もり体質になってしまい、その上ここまでの会話で推測できる通り不登校少女でもある。去年度も滅多に登校せず、僕が無理矢理家に突撃して連れて行かなければ、危うく留年するところだった。
女子にしては長身で、手入れしていないにも関わらず艶のある黒髪は腰まですらっと流れるように伸びている。足も長く、身体が全体的に細いので、贔屓目抜きにしてもモデル体型だろう。僕は女性ではないため芯から乙女心を解することはできないが、一般女性から見ると、咲のスタイルは羨望に近い念を抱かれるに相違ないだろう。
いつも思う。
容姿は魅力的にも関わらず、対人関係をごみ箱に投げ入れて損をしている。その上、やる気なく半開きの目の下にはうっすらと隈が浮かび上がっており、より陰気な雰囲気を加速させているようにも見えた。その気になれば充実した青春を謳歌できるであろうに……。
「でも」と咲はなおも食らいつく。「人の物を奪うまではやり過ぎだよ。これ、犯罪」
指摘は確かに的を射ているが、将来有望の自宅警備員予備軍の彼女に言われたくはない。
僕は精々悪戯な笑みを浮かべる。
「うるさいな。仕方ないだろ。言っとくけど今年は留年寸前なんかにはさせないよ。必ず皆勤させてやる。覚悟しておけ」
そう言うと、咲は拗ねたように眉に皺を寄せ俯いてしまった。面倒なことになった、と焦るような気持ちが、その表情に如実に表れている。
その理由が分かるからこそ、僕はそれ以上念を押すことはできなかった。
最近建て直されたばかりの真新しいJRの駅を過ぎると、通学路は列車通学の高校生の姿でごった返し始める。あれやこれやと僕に文句を言っていた咲は彼らの姿を視界に入れるなり、母親に甘える子猫のように寄り添ってくる。人の目もあるし突き放してやろうかと考えたが、すぐに戻ってくるのは目に見えているため、諦めてそのまま寄り添わせることにした。
悟。これが僕の名だ。由来は、周囲の痛みに気付く子になりますように。決して妖怪サトリではないので悪しからず。
僕こと神上悟と咲は幼馴染みで、それこそ物心ついた幼い頃から一緒にいた。僕と咲と姉さん。何をするにもこの三人で、家族ぐるみで旅行に行くことも……。
「……」
瞬間、ふと嫌なことを思い出しそうになったのを、軽く数回かぶりを振ることで振り払う。咲は怪訝な表情を浮かべていたが、男子生徒が横切るなり、すぐに警戒体勢に戻った。
赤の他人なのだから警戒する程でもなし、さながら野良猫のようだ。背中にぴったりとくっつき、周囲に人陰などまばらなのにも関わらず、異国の地に連れてこられた捕虜のように忙しく周囲を見渡している。
その時期を見計らっていたかのように、不意に背後から誰かが駆けてくる足音が聞こえた。次第に足音は大きくなり、僕のちょうど真後ろでぴたりと止まる。
「うぐ」
と背後で変な呻き声が聞こえた。どうせ対人恐怖症の咲が、突然の来訪者に猜疑心が募っているのだろう。
だが不審がる必要もない。この時間帯からして僕らに駆け寄る相手はただ一人。
「おっす、神上」
呼ばれて振り返る。そこには髪を金髪に染めた、いかにもチャラチャラとした男子生徒がいた。
「おはよう」
僕も彼に倣って挨拶する。
「ああ、おはよ」と新は笑った。「サッキーもおはような」
ちなみにサッキーとは咲のことである。見知った人物だと分かり、咲はほっと胸を撫で下ろした。
竜崎新という金髪の男は、一見チャラチャラしてそうに見えるが、試験及び模試では常に不動の一位の天才少年である。だが行動などが幼稚なため、阿呆という言葉がこの上無く相応しい。さらに言うなら容姿は端正の一言に尽きるのだが女子にモテない。理由はそのセンスにあるのだが、今は伏せておこう。
まったく。どうして僕の周りには咲や新、そして湊のような変人しかいないのだろうか。悲しくて涙が出てきそうだ。
「神上。今、失礼なことを考えなかったか?」
「気のせいだろ」
新の台詞を即刻切り捨てたと同時に、僕らの通う高校、私立河江高校に到着する。校門から玄関の間には一直線に繋がるコンクリート詰めの通路があり、左右には桜の木が等間隔に植えられている。新たな始まりであるこの日に相応しく、桜は満開に咲き誇り、花びらを紙吹雪のように散らしていた。
「相変わらず、この学校の桜は凄いな」
多くの生徒が桜の並木道に見惚れる中、新もまた満開の桜を眺めながら感慨深げに呟く。無論、それは僕もまた然り。
「だよな。去年の入学式の時を思い出すよ。あの時も呆気に取られたもんだ。どう、咲。来てよかったでしょ?」
きっと咲も満開の桜に目を奪われていることだろう。故に僕は彼女に声を掛け、また振り返った。
だが。
「……」
もはや溜め息を吐く時間すらも勿体無い。僕は笑みを消すと、どこに隠し持っていたのか分からない携帯ゲーム機を無言で咲から取り上げる。
「あ、何するの?」
と咲はゲーム機を取られた理由を解せず、困惑したように僕を見上げた。
「咲さん。貴女は学校に何をしに来てるんですか?」
咲の問い掛けには応えず、低い声色で逆に問い詰める。しかし彼女は臆することもなく、その口からつらつらと嘘八百を並べた。
「友情を育みに」
なるほど。はぐらかそうとするならば、思う存分言い訳を叩き伏させていただこう。
「嘘だな。僕の知る限り、お前に友達はほとんどいない」
「ひどい。少しくらいはいるし」と彼女は頬を膨らます。「なら甲子園を目指すために」
「頑張れマネージャー。あと河江高校の野球部は熱血だが、人数が少なくて廃部寸前だからな」
「目指せ、武道館」
「軽音部は去年廃部になったな」
落ちる静寂。沈黙すること数秒、やがて咲は両手を後ろで組むと、
「てへっ」
小さな舌を出し、屈託のない笑顔でおどけて見せた。
その笑顔が普段の彼女からは想像できない程可愛らしかったので、こちらも礼を尽くし、にこやかな笑顔を浮かべてからその可愛らしい額に強烈なデコピンを一発お見舞いした。
びしっと鈍い音が響く。
「痛い……」
後ろに数歩よろけると、彼女はうずくまるなり自身の額を懸命に擦り始める。おもむろに近付くと、そのまま僕も腰を降ろす。行き交う生徒たちが奇異の眼差しを送ってくるが、今は気にしない。
「痛くしたんだから当たり前」と僕は言った。「それに先生に見付かったら没収されるんだから、先に注意してあげただけ感謝しなよ」
「それでも悟、ひどい」
涙目になった咲の腕を掴み、引っ張って立たせてやる。どうやら本気で痛かったらしい。少しやり過ぎたようだ。
「悪い。次からは加減するよ」
「ん。あ、でも結局することに変わりないんだね」
愚問だな。
戯れ合いを手早く済ませ、何事も無かったかのように僕たちは再び歩き始める。暫し歩みを進めると、玄関前の掲示板に人が多くたむろっている光景が見えた。
「お、クラス編成表はあそこか」
新の言う通り、貼り付けられていたのはクラス編成表らしく、そこから喜ぶ声、悲しむ声など十人十色の声が轟いている。
ハッシーとは別のクラスか。
部活で会えるさ。
やった、同じクラスだ!
なかなかいいんじゃない?
えー、私、一人じゃない。
うちら一緒やんっ。
など、思い思いの声が飛び交う。
「よし、行こうぜ」
「あっ、おい」
高らかに叫ぶと、無謀にも新は人混みの中に割って入って行った。まだ人は多過ぎる。無理して人混みに埋もれなければいいのだが……まあ、僕には関係ないか。
しかしクラス編成はどうなっているのだろう。気になる、と言うか分からないと教室に辿り着けないから困る。こうなってしまっては遅かれ早かれ人混みに突入する羽目になっていた。取り敢えず新の生還を咲と共に待つことにする。
「どうやら同じクラスのようだな」
隣から男子の声。
「へえ、そうなのか。奇遇だな。……って、うわっ」
声のした方に顔を向けると、いつの間にか僕と咲の間に一人の男子が入り込んでいた。思わず頓狂な声を上げ、後ろに二・三度よろけてしまう。
「なんだ。その驚き様は」
不機嫌な声色。いつの間にそこに居座っていたのやら、男の声はどことなく拗ねたような意味を滲ませているようだ。刹那、遂に僕も霊感の才を発揮したかと得意になったが、その男はよく知る者であった。
「ああ。なんだ、元木か」
男子の正体が顔見知りであったことに安心し、ほっと一息。
「なんだとは失礼だな」
感情を判別しにくい、困ったような笑ったような、そんな微妙な表情で男子生徒が言う。
元木海斗。それが彼の名前だ。成績は中の中。ルックスも中の中。存在感は下の下。存在感の無さを除いたら、普通の塊のような男だ。
常にやる気なく半開きでたれ目であり、かつ視力も悪く黒縁眼鏡をかけている。髪は天然パーマで無造作にはねている箇所も多々あるが、このようななりでも何と生徒会役員で、さらに副会長というので驚きだ。しかも現会長からのお墨付き。いやはや、人間、見た目だけではないようだ。
「そういやさ」と僕は言った。「元木が言うには同じクラスなんだってな。何でそんなことが分かるんだよ。もうクラス編成表を見たの?」
「これだよ」
相変わらず覇気の無い声色で僕の問いに短く返しながら、元木は小さな紙切れを僕と咲に手渡す。覗き込んむと、そこには沢山の名前が規則的に割り振られた図がプリントされていた。
これは……。
「クラス編成表だね」
同じように覗き込んでいた咲の小さな呟きに元木は頷く。
「ああ、クラス編成表だ。掲示板だけでは見えない人もいるだろうからと、こうやって今年度からクラス表をプリントしたものを配っているんだ」
なるほど。これなら、わざわざ人混みに突っ込んで見に行く必要もないし、何より手間も省けて楽の一言に尽きる。よく考えたな、生徒会。
「それじゃ、クラス編成表も手に入ったことだし教室に行くか」
用件が済んだ今、わざわざ玄関前に突っ立っている理由もない。生徒会の仕事が残っている元木に「頑張れよ」と労いの言葉を贈ってから、僕は踵を返して玄関口に向かう。
と、不意に咲が僕の制服の裾を掴んだ。
「え、ちょっと。竜崎くん、どうするの?」
言われて新が人混みの中で熾烈な争いを繰り広げていることを思い出す。ここまで一緒に来たのだから待ってやるのもいいが、
「まあいいんじゃない?」
ぶっきらぼうに僕は応える。一人で突っ走って行った新には、人混みの波と存分に戦っていただこう。
一先ず僕は既に手の中にあるクラス編成表の紙面に視線を落とす。A組から順にしばらく自身の名前を探していると、やがて二年C組の欄に神上悟、元木海斗、竜崎新、石沢咲、琴吹湊の名を見付けた。
刹那、周囲のざわめきが消えたような錯覚に陥る。
まさか、そんな馬鹿なことはないだろう。昨日まで春期休養中の課題の追い込みをしていたため疲れ目になっているに違いない。僕は目頭を強く抑えると、念には念を入れ一応目薬も手早く差しておいた。
見間違いだろうと思い、再度プリントに視線を落とす。
神上悟、元木海斗、竜崎新、石沢咲、琴吹湊。
おかしい。どうやら疲れ目は深刻なようだ。ひょっとしたら角度が悪いのかもしれない。今度は下から覗き込むようにして読む。
神上悟、元木海斗、竜崎新、石沢咲、琴吹湊。
…………。
沈黙。
「なあ、元木。僕も明日から不登校になるよ」
じゃっ、と爽やかに右手を掲げて回れ右をするも、
「真実から目を背けるな」
と、鞄を掛け直し玄関とは逆方向の校門に向かって歩き出そうとした僕の肩を、諭しながら元木が掴む。
真実とは何とも儚いものだ。人間、理想の世界と真実の世界、どちらがよいかと問われれば、大半の者は理想の世界と答えるであろう。それほど真実は残酷であり、それ故に文学や宗教などが発展し、今尚現代に根強く理想の世界が具現化して存在しているのだ。
故に僕が真実から目を逸らしたのも人間としては当然の行動であり、彼に注意される程の事でもない。
が、元木は理想への道を無慈悲にも阻みにかかる。
「確かに神上くんにとっては苦手な存在かもしれないが、そこまで琴吹さんを邪険に扱わなくてもいいじゃないか」
何だと?
反射的に校門に向けて忙しなく動かしていた足を止める。先程の元木の台詞は聞き捨てならん。僕は振り返るなり、人差し指を元木の胸元に何度も突き付けた。
「何を悠長なことを。元木は奴の恐ろしさを自らの身をもって知らないから、そんなことが言えるんだよ」
思わず声を荒げると、やれやれと言わんばかりに元木は肩をすくめる。
さて。先に紹介しておくが、琴吹湊はとんでもない女だ。容姿は至って普通の女子生徒のように見えるが、如何せん、可愛いものに目がないのだ。
まあ、そこまではいい。可愛いところだと思う。許容範囲内である。しかし、何故かあいつは事あるごとに僕や新をおかしな遊びで振り回すのだ。曰く「面白いから」。こちらとしては全くもって面白くも何ともない。あえて前例を挙げるならば、去年の文化祭では僕と新を無理矢理女装させ、そのまま学園内を徘徊させたのだ。誰にも正体が見抜けなかったのは唯一の救いだが、もし誰かにばれていたと思うと、考えるだけでも恐ろしい。
つまり琴吹湊とは理不尽の代名詞であり、かつ防衛本能を剥き出しにして臨むべき相手であるのだ。新も湊の魔の手による被害者であるため、今では良き戦友として末長い付き合いを約束している。
だが唯一実質的な被害が無いのが、この元木海斗であるのだ。
「元木にこの気持ちがわかるのか。たまにはお前も湊に襲われたらいいのに」
と呪ってしまうのも致し方がない。
荒れる僕を見かねてか、不意に咲が僕の制服の裾を引っ張った。
「まあまあ、落ち着いて」
「でもなあ。ううん。……うん」
彼女の穏やかな、マイペースな声で正気に戻る。
よもや誰よりも心配するべき咲に注意されるとは、どうやら僕もまだまだ未熟なようだ。感謝の言葉を口にするのも、何故だか気恥ずかしい。
一つ咳払いをする。
「ああ、悪い。兎に角、僕にとって湊は畏怖すべき危険人物なんだ。だから奴を見掛けたら一先ず逃げろ。そうでもしないと身の安全は保障できない」
こんな話を続けていても僕の古傷を抉るだけだ。手早くこの話を切り上げようと、元木の方に振り返る。
すると。
「あ」
自分でも情けなく思える声が洩れた。
その時、視界にあってはならないものを捉えたのだ。冷や汗が背筋を伝い、瞬時に走馬灯のようにトラウマが脳裏を駆け巡り始める。
事あるごとに人を面倒ごとに巻き込み、去年の文化祭ではトラウマを受け付けた張本人。美しい容貌とは裏腹に、腹の内には正気を疑いたくなる性癖を抱いた少女。
僕のトラウマそのもの、琴吹湊がそこにいた。
瞬きをするよりも早く、全身に危険を知らせる警報がけたたましく鳴り響く。内なる自分がやばい、早く逃げろと囁き掛ける。春休みという長期休暇を挟み遂に明けた今日、下手したら会っただけで彼女のフラストレーションが爆発しかねない。
逃げろ。
脳がそう命令を下した瞬間、僕は踵を返し走り出そうと試みた。
しかし浅はかだった。
「どっこ行っくの?」
眼前に満面の笑顔。
「うわっ」
素っ頓狂な情けない声が上がるなり、その反動で二、三歩後方によろけてしまう。危うく尻餅をつきそうになったのを、背後の元木が間一髪支えてくれた。
なんてことだ。最初から彼女は僕たちの存在に気付いていたのだ。裏をかいて逃げようと試みたが、先に先回りされ、最高級の笑顔と獲物を捕えた猟師さながらのぎらぎらとした瞳で進行方向を阻まれる。
全身に悪寒が走った。
琴吹湊は先程述べた通り容姿は他を卓越して優れている。身長は女子にしては高めであり、出る箇所は出て、引き締まっている箇所は引き締まっておりスタイルもよい。髪はポニーテールで結われており、活発さを象徴するように左右に揺れる。
うむ。容姿は非常にいい。しかし、やはり問題は中身だ。
湊は男女が最も意識するであろう距離感を一切気にすることもなく僕に詰め寄り、からかうように顔を近付かせる。間接的ながらもその迫力に圧倒されたのか、ずっと背後で支えてくれていた元木は無情にも危険を回避するように忍び足で僕たちから離れていった。この裏切り者め!
元木という壁を失った今、とにかく後ずさるしか僕には手がなかった。しかし相変わらず湊は笑顔のまま僕に詰め寄る。その度にこちらは後ずさっているため、いつ桜の木と衝突するか分かったものではない。
「今、逃げようとしたよね」と彼女は悪戯な笑みを浮かべる。「ねえ。どうして?」
「してない。してないぞ」
我ながら白々しい。目を逸らし冷や汗を流しながら弁解しては、説得力は皆無に等しいではないか。何よりこの行動はより彼女の笑みを濃くするだけである。こやつには如何なる手段、言い訳も通じないのだ。
苦悶の表情を浮かべると、性悪にもさらに笑みが濃くなる。
嫌な予感。それは当たらなくていいのに、どうしてか当たってしまう。
「アタシさ、こんなの持ってるんだけど」
鞄から取り出した物、それはケースに収納された一枚のDVDだった。
「何だよ、それ」
内心予想はついている。疑う余地もなく僕にとって不利になるものが撮影されているに違いない。何せこの場面で取り出すということは、則ち僕を陥れるという下心があるからだ。
妖艶に彼女は微笑み、そのやわらかな唇にケースを添える。
「去年の文化祭、通称河江祭でのサトルの女装姿を収めた長編ドキュメンタリーだよ」
どうかこの時の僕の心情察していただきたい。こちとら一刻も早く我が忌々しき黒歴史を闇に葬りたい所存であるにも関わらず、この悪女はそれを許すまじと言わんばかりに記録媒体にて保存し、得意気に公に晒しているのだ。憤りを感じるのも無理はないだろう。
軽蔑の念も込めて湊を睨み付けるが、然りとて彼女の前で威嚇など無意味な行為だ。白々しく口笛まで吹くではないか。
「そんなもの捨ててやる」
流石に頭に来るのも致し方無い。何とかしてDVDを奪おうと手を伸ばすが、しかし無情にも紙一重で交わされる。
身軽に一二度バックステップで後退すると、彼女は短いスカートを翻した。
「残念。これは琴吹家の家宝として受け継いでいかせます」
「そんなものを家宝にするな!」
未だに人の姿が際立つ玄関前に、一人の男の叫び声が響いた。
3
その後の経緯はどうか察していただきたい。彼女の毒牙にかかったが故に貴重な時間を無駄に費やしてしまい、教室に辿り着いた時には既に始業のチャイムが鳴り終えてしまっていた。まだ先生が教室に居ないことが不幸中の幸いとでも言えようか。然りとて進級初日に遅刻したことに代わりはない。
余談であるが新は僕らが戯れていた隙にクラス編成表を確認し戻っており、元木の手に握られていたプリントを目に入れるなり「え、俺の努力って何?」とあからさまに肩を落とした。いやはや御愁傷様で。
進級してクラスが編成されたからと言っても、教室の造りは去年とさほど変化はないようだ。
二年C組の教室には僕らを含め二十五人の生徒の姿があった。机は規則正しく一列五人の五列に並べられており、また窓際側の黒板の脇には出入り口のスライドドアとは対照的な古びた扉が存在している。各教室には必ず小さな準備室が設けられており、そこには普段授業で使う辞書や資料が置かれているのだ。このように便利な教室があるのも河江高校の特徴の一つでもある。
去年と同じ造りの教室。ただ一階上に移動しただけなのだが、その光景は真新しく見える。
何せ今日は始業式。新しい一年の始まりを告げる大切な日なのだ。クラスメイトの面構えも変わり、それ故に何処か居心地の悪さと期待を感じる。
しかし記念すべき行事であるにも関わらず毎度のことながら始業式とは名ばかりの風景のように思え、時間に流されるままに過ごしていると只でさえ短い式は終わりを迎え、早くも下校となった。
放課になるなり新しい学友たちは少ない顔見知りに声を掛け、有意義な下校を楽しむために足早に教室から姿を消す。また傍迷惑な湊もバイトがあるとのことで今日は直ぐ様帰路についたようだ。平和な放課後に敬礼。
特に学校に居てもすることもないので、僕も鞄に手を掛けて帰ろうとする。結局その行為は去年と何ら変わらない日常に埋め込まれた習慣の一つにすぎなかった。
クラスが変われば何かが変わるんじゃないか。無意識の内に心の何処かで淡く期待していたが、残念ながら一年生の頃と同じ風景。
そう。何も変わっていない。
常に自分から誰かに近付こうともせず、また知られようともせず、そうやって一線を引いて生きてきた。特別なきっかけがなければ親しい友人はできず、できたとしても全てをさらけ出すに至らない。特別な『誰か』は未だに僕の前に現れないのだ。
いつまで待てば現れるのだろうか。明日かも十年後かもわからない来る日を夢に見ながら、僕は大人になっていくのだろうか。
なんて、がらにでもないことを考えてみる。
「もう帰るのか?」
その言葉が僕にかけられたものだと気付くのに、暫しの時間を要する。
一番通路側の列の最後尾に割り振られた席、そこが僕の席だ。声は隣の新の席から響いた。
「うん」と僕は答える。「特にすることもないしね」
「そうか。なら一緒に帰ろうぜ。サッキーも帰りたげにうずうずしてるようだしな」
そう溢す新の視線は窓際の咲に向けられている。確かに彼女は異国の地に一人放り込まれたかの如くしきりに周囲の反応を気にし、小動物のように身を震わせていた。
いくら何でも緊張しすぎだろう。
「咲、帰るよ」
溜め息混じりに声を掛けると、彼女は「待ってました」と言わんばかりにこちらに駆け寄ってくる。
まったく。
元木にも声をかけてみたが、生憎生徒会の仕事があるらしく、必然的に三人で教室を出て帰宅の路を歩むことになる。
さて。この咲、新、湊、元木の四人が僕が唯一見付けた信頼できる小さな輪だ。出会った経緯はまた追々。
彼等と過ごす時間はあまりにもありふれた、探せばどこにでも存在する光景だ。特別だと思っていても僕らがしているのは青春の模範でしかない。
だからこそ思うのだ。今を楽しく生きれたら、それでもいいよな。応えなどもちろん誰も返してくれるはずもない。
でも、いいよな。それで笑っていられるなら。
そんな何もないはずの高校生活に変化が起きたのは、翌日のことだった。