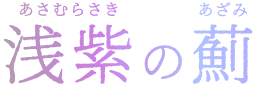浅紫の薊 序章
僕は無心の人形だった。
回想を始めるにせよ、真っ先に記しておきたい一文は一先ずそれだった。
ねえ、と誰が聞いているのかも分からない中、そこに『誰か』は居ないのかもしれないのに、僕は虚空に問い掛ける。真っ赤な空を見たことがあるだろうか。僕は、ある。
何を馬鹿な事を、と呆れるかもしれない。しかし、あの日の空は疑う余地も無く真っ赤に燃えていた。本当に空は青いのかと疑いたくなる程、濃く、深く、溢れ出した血のように深紅に染まった空。そんな生々しい空へと、どす黒い煙が吸い込まれるように昇っていき、遠くからは忙しなくサイレンの音が轟いていた。
おもむろに目を開けると、一面に真っ赤な世界が広がっていた。
見渡しても誰も居ない。あるのは異形と鉄の塊だけ。嗅いだこともない異臭が辺りに充満しており、思わず鼻を覆った。
揺らめく赤、腐敗した臭い、滴る赤黒い液体が、この世界を支配している。そこはさながら地獄のようだ。
そんな世界を、僕はおぼつかない足取りで歩く。
身体中の節々が痛い。炎の熱さに皮膚が焼かれるようだ。そして何よりも悲しい。身体中に刺す痛みよりも、内から悲しみが溢れ出ることに辛さを覚える。
みんな、どこに行ったの?
誰も居ないと知りつつも、僕はそう問い掛けずにはいられなかった。つい先程まで近くにあったはずの笑顔が、幻のように溶けて消え去る。まだ事態を呑み込めていない幼い僕にその理由を伺い知る術はなかった。
然りとて、もう誰も居ない事くらいは薄々分かっていたに相違ない。それでも尚、希望を手探りに探すように僕は願い続けた。不思議と涙は出ず、悲鳴を上げる気力もない。
不意に誰かの悲鳴がこだました。
紅の空に立ち込める排煙の根本から悲痛な誰かの泣き声が響いている。あそこに誰かがいる。それだけを心の支えとして、僕は鉛のように重くなった足を引きずりながら前へ前へと進む。
お願い、誰か現れて。誰か声を掛けて。いや、声を掛けなくてもいい。ただ側にいてほしい。それだけで救われるんだ。
排煙の根本に近付くにつれて悲鳴は次第に大きさを増す。相手の都合なんて今は二の次だ。ただ寄り添える相手が欲しいというエゴイズムだけで歩みを進める。
安心したいんだ。だから誰か。
誰か、僕の側に……。